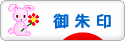栃木編をまとめる前に…
【栃木】
栃木県小山市間々田の
間々田八幡宮の
ステキな新作【御朱印帳】![ラブラブ]()

令和2年1月よりお受けできます![音譜]()

【間々田八幡宮 御朱印帳】
表紙は
北極星が真上に輝く社殿
裏表紙は
じゃがまいたの祭神
八龍神社の紋章が
デザインされています![音譜]()

【間々田八幡宮 御朱印】 【間々田八幡宮 御朱印】
【間々田八幡宮 御朱印】 【厳島神社】![]()
特別な和紙で奉製された
子年とじゃがまいたの
コラボデザイン![音譜]()

江戸時代から続く伝統行事
「間々田のじゃがまいた」
2019年3月
国重要無形民俗文化財に
指定されています。
毎年5月5日
地域を挙げて行われる奇祭で
各自治会から
全長15メートルの巨大な
「蛇」が7体集まり
境内で神事を行った後
弁天池で蛇が水しぶきを上げる
「水飲みの儀」が
行われるそうです。
3月の月替わり御朱印は
3月前半(15日迄)は
「梅と市杵嶋姫命」
3月後半(31日迄)は
「桜と息長帯姫命」
との事![!!]()

市杵嶋姫命の御朱印に
押してある印は
かつて使用していた古い印で
持ち手が折れているため
今回だけの復活だそうです。
詳細などは
をみて下さいね![ウインク]()

【狛犬】
【御祭神】
誉田別命
息長帯姫命
今から約1300年ほど前の
奈良時代中期の創建と
伝えられてる古社。
百足退治の伝説でも知られる
武将・藤原秀郷が
当八幡宮ほか沿道の神社仏閣に
戦勝を祈願し
ご神徳へのご恩返しとして
神社にご神田を奉納。
以降、この一帯は
飯田(まんまだ)の里と
呼ばれるようになったそうです。
1189年
源頼朝がこちらに参拝した際に
境内に松を植え
その松は
1905年に枯死するまで
『頼朝手植えの松』
として
大切に守られていたそうです。
江戸時代に入ると
日光街道が
幕府の手により整備され
この地がちょうど
日光と江戸の中間点となるので
地名が
飯田から間々田(ままだ)
へと改められました。
松尾芭蕉も宿泊するなど
日光街道の宿場町として
大変栄え
朝廷が日光東照宮に
毎年例幣使を遣わす折には
道中必ず参拝するのが
習わしだったそうです。
【御祭神】
田心姫命
湍津姫命
市杵嶋姫命