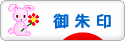【宮崎】
【串間神社 御朱印】
【串間神社 御朱印】
【串間神社 御朱印】
秋季大祭特別朱印
【手水舎】
【拝殿】
強めの雨が降ってきたので
今回、写真は殆ど撮っていません

【本殿】
【御祭神】
彦火火出見尊
主祭神は彦火火出見尊。
外に十二柱の神々をお祀りするので
十三所大明神
と称されていた神社。
「神名録」では
山幸彦(主祭神の別名)が猪・雉など
獲物の多いこの地を狩場として通われた
仮宮所で穂穂宮と称し
その宮跡を斎き祀った
と伝えられています。
正平14年(1359)には
野辺盛房が十三所大明神の社殿を再興。
その後、
応仁元年(1467)・永正12年(1515)
天文13年(1544)と
島津氏により再興された記録があり
永保6年(1563)には
領主・島津忠親の奏請により
神階宣下勅額を賜り
藩主、世々、福島総社として尊崇され
秋月領となっても
元和7年(1621)から慶應2年(1866)まで
再興が続きました。
明治維新後は
福島・北方・大束・本城・都井
市木六ヶ町村の氏神として崇拝。
明治5年(1872年)
神社改革の際、串間神社と改称し
郷社に列せられました。
明治40年(1907)
旧六ヶ町村の出資で社殿を改築されましたが
老朽化し損傷が著しく
平成元年
串間市が市制35年の記念すべき年に
奉祝記念事業として
改築奉賛会を設立。
平成元年6月、工事に着工
同年10月に竣工。
農業の神様・学問の神・商工の神として
多くの崇敬を受けています。
関連記事
鵜戸神宮
一葉稲荷神社
青島神社
野島神社
インスタはこちら