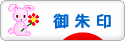【滋賀】
滋賀県大津市園城寺町の
皇室ゆかりの門跡寺院
総本山
圓満院門跡
以前お受けした
【圓満院 御朱印】
以前お受けした
【圓満院 御朱印帳】
【圓満院 御朱印帳】
種類は
孔雀・大津絵の鬼の念仏
藤娘の3ありました![音譜]()

【大玄関】
大玄関の前の白砂の手前には
青竹の結界が張られ
天皇陛下が行幸された場合のみ
その結界が開けられます。
圓満院は
987年、村上天皇の第三皇子
悟円親王により
創立された三井寺山内にある
天台宗の門跡寺院。
三井三門跡のひとつで
開基当時は
平等院と呼ばれていました。
藤原道長が
宇治に建てた別荘を
藤原頼道の時代に
寺院にするよう命令が下され
平等院(のちの圓満院)の
明尊大僧正により完成。
悟円親王の子
永円親王が初代院主となり
三井平等院の名前を
宇治に譲り
現在の宇治平等院の初め
となっています。
三井平等院は
明尊大僧正により圓満院
と命名され
室町時代後期まで
通称 三井平等院と呼ばれる
悟円親王をはじめ
とした
歴代皇族が入室する
門跡寺院となりました。
【宸殿】重要文化財
1619年、徳川幕府第2代将軍
徳川秀忠公の息女
和子姫が後水尾天皇の后
として
御所に入る際に建てられ
1647年
京都御所より譲り受けた建物
明治11年、明正天皇
明治13年・45年には
当時東宮でいらっしゃった
大正天皇が行幸された
全国に
17ヵ所しかない由緒ある
門跡寺院です。
~全国にある門跡寺院~
東叡山輪王寺 (東京)
日光山輪王寺 (栃木)
円満院 (滋賀)
青蓮院 (京都)
妙法院
実相院
滋賀院
三宝院
【王座の間】
後水尾天皇が座した
玉座を配した「玉座の間」
と言われる
池泉鑑賞式の庭園
江戸初期に東海道五十三次の
大津の宿場で軒を並べ
街道を行き交う旅人等に
縁起物として
神仏画を描き売ったのがはじまり。
1804~1829年には
「大津絵十種」と呼ばれる
代表的画題が確定。
画題は増え続け
幕末には最盛期を迎えましたが
画題の簡略化に伴い減少し
現在では
100余種とされています。









































 近江聖徳太子霊跡めぐり
近江聖徳太子霊跡めぐり